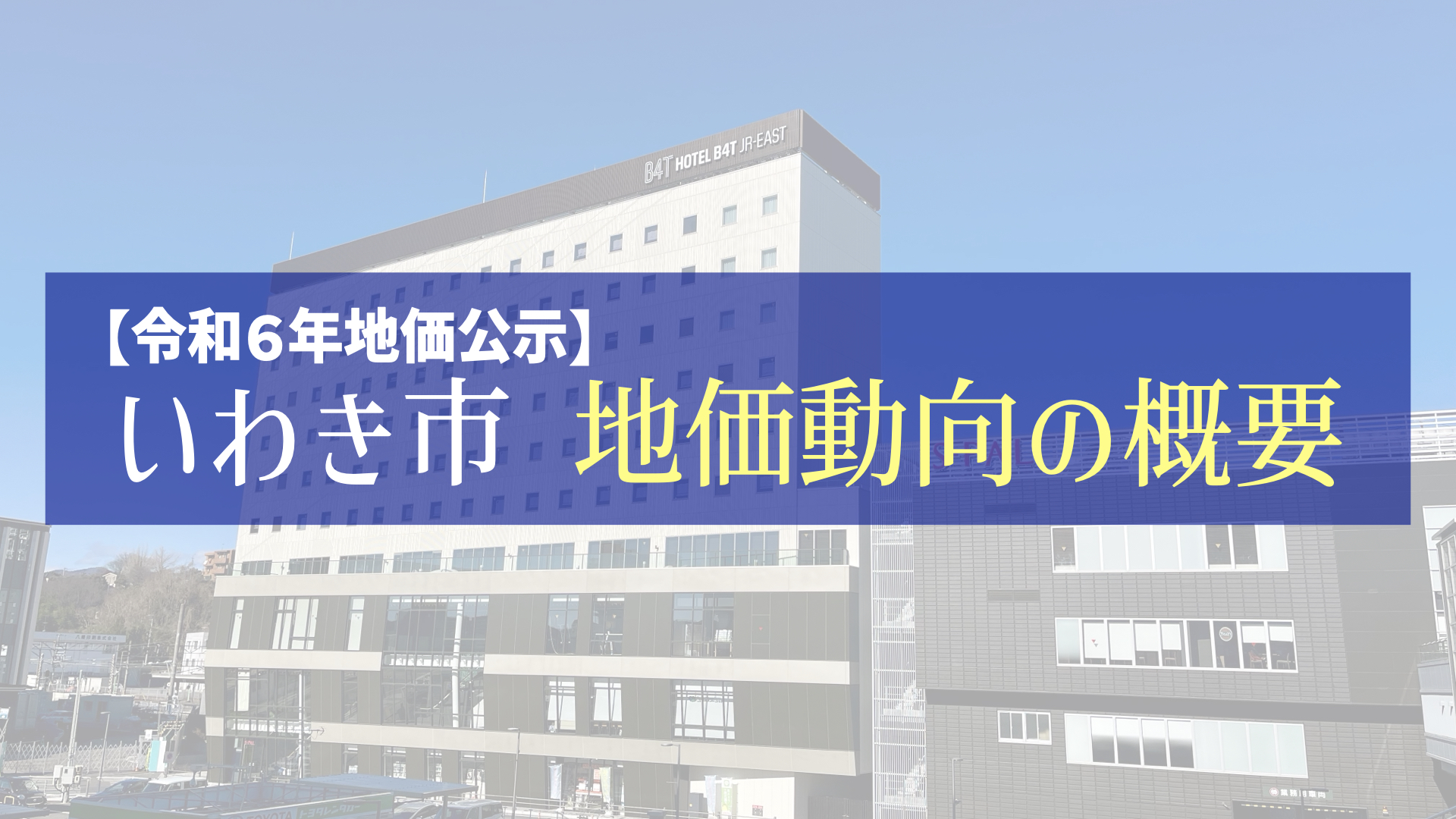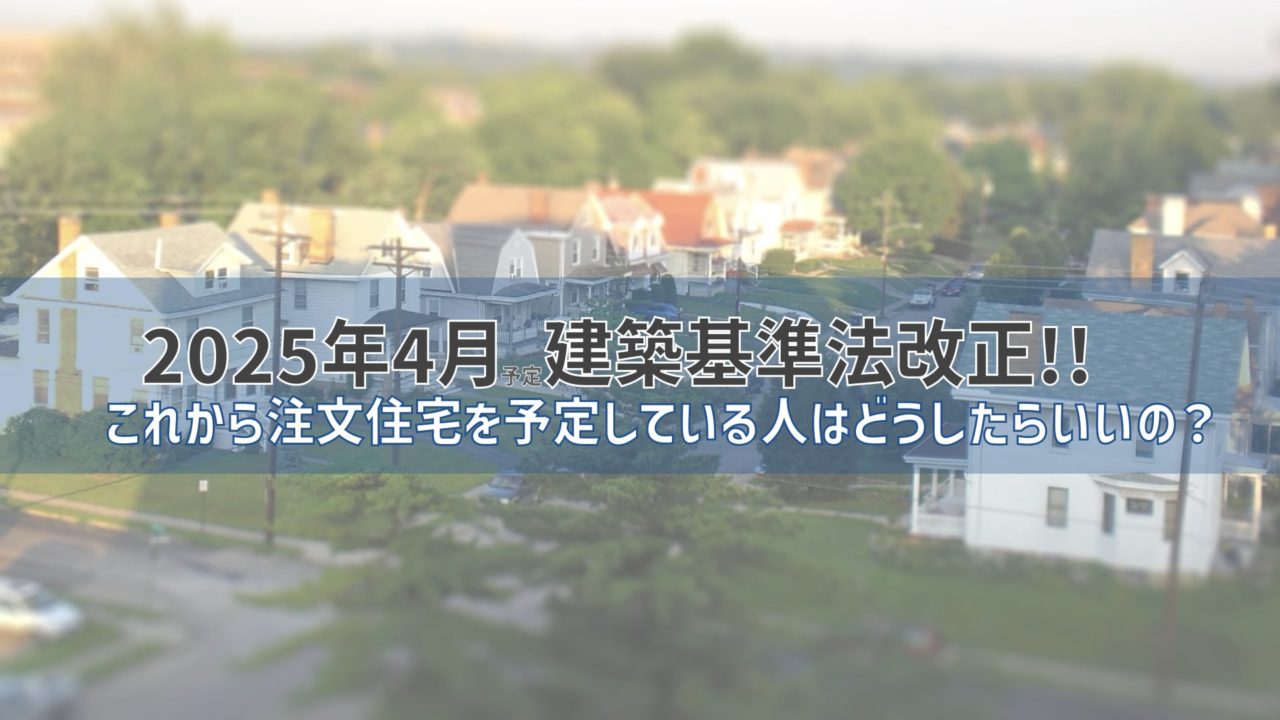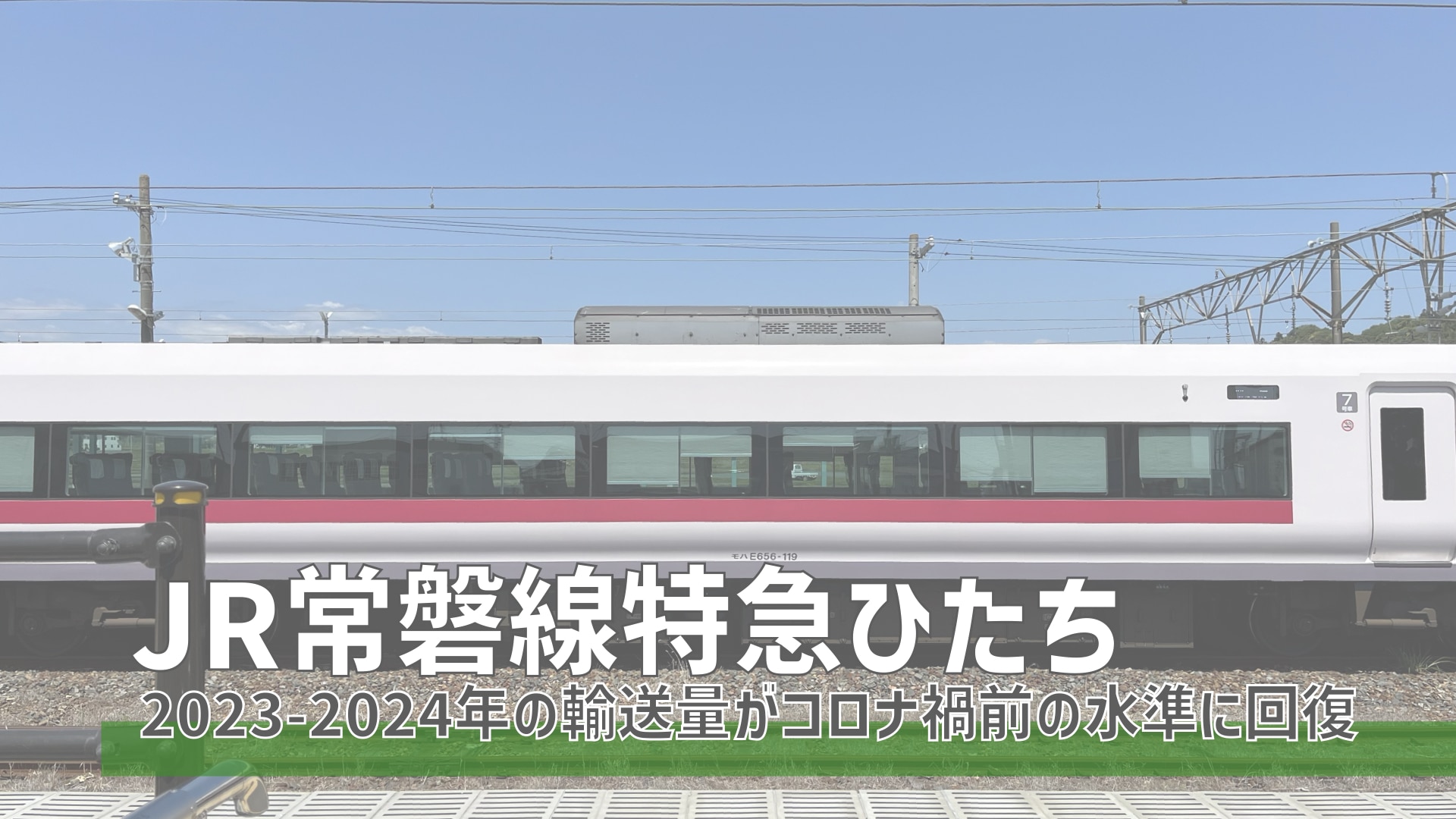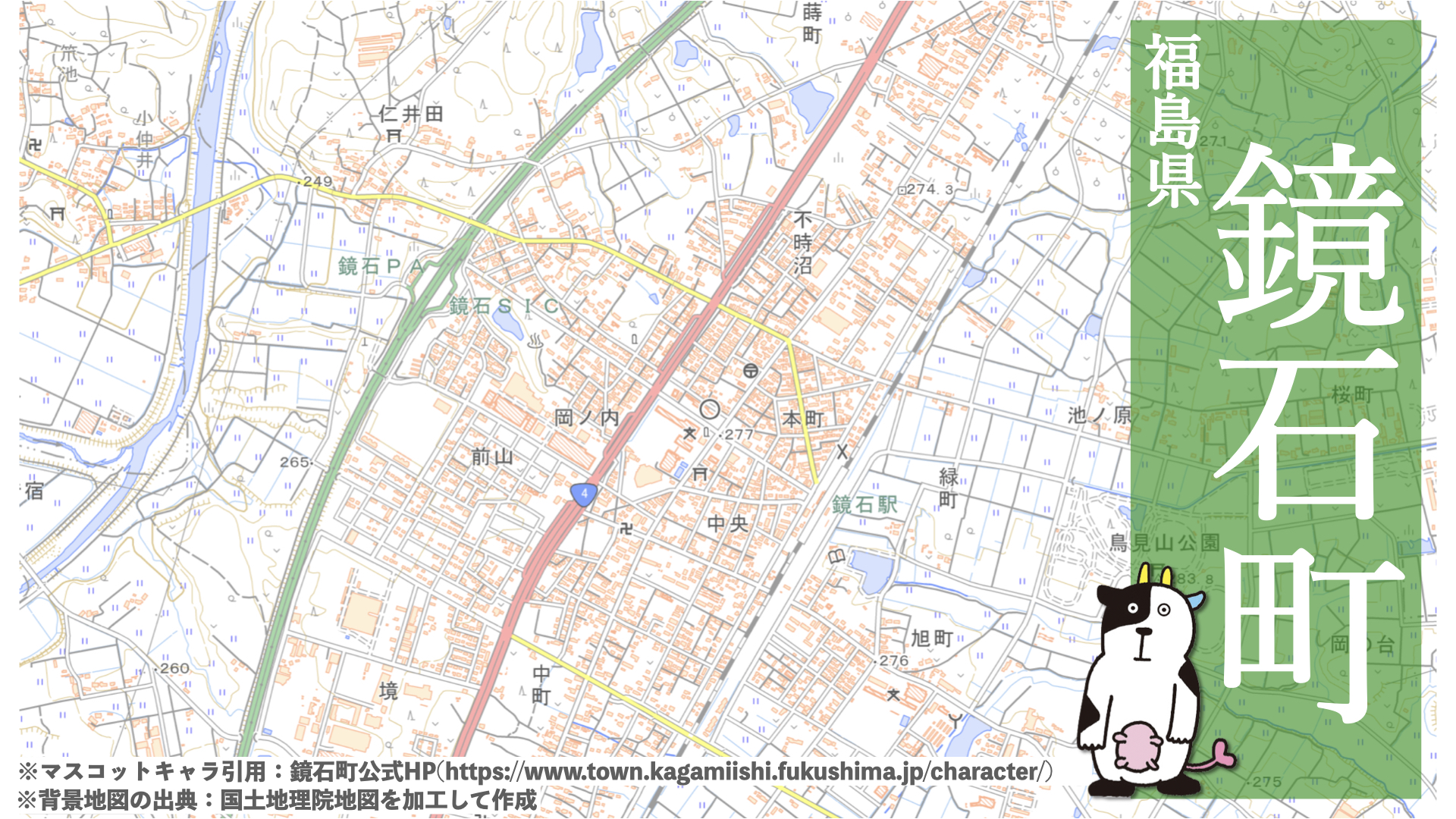茨城県高萩市の歴史的な観光地の一つである『松岡城址』について考えた事を勝手に整理しています。
いつも当サイト(UPS)をご覧いただきありがとうございます。
当サイトでは”まち”の稼ぐ力を伸ばすために、水戸から仙台エリアにかけての街の魅力や情報を発信しています。
現在はWEBを中心に活動していますが、近々、拠点を設けてまちづくりを行っていきたいと考えていますので、応援して頂ければ嬉しいです♪→サイトのブックマーク登録&インスタフォローをお願いします☆エンジェル投資家さんも随時募集しています♪
松岡城とは?

松岡城は、岩城領(福島県浜通り)の一部だったそうで、大塚氏という方が1,596年に岩城領折木(福島県広野町)に移るまでの間、戦国時代の山城として使われていたそうです。
その後、岩城と佐竹(茨城)は秋田に移ることになったため、戸沢家が1,602年に入った後、山城から近代の平山城として整備がなされます。その後、戸沢家は1,622年に新庄に移ったため、水戸藩領地となり、水戸藩家老の中山氏の居城となり、幕末まで水戸藩の支城として存続します。
筆頭家老の知行地だったようですが、中山氏は元々徳川家の家臣団で、武州(武蔵野)の出身で徳川一門の強化を図るために水戸家の藩祖である徳川頼房(徳川家康の十一男)に付いて現在の北茨城・高萩周辺を領地としたそうです。歴史ありますよね。
実際、城下町整備(武家屋敷)もされており、石畳と塀は立派です。見に来てただ帰るだけとなってしまうのはもったいない!!

推測:行政の担当者が変わって中折れ?

行政の宿命ですが、行政担当者の知識・能力がそれぞれ異なるため、担当者が異動すると全く活動されなくことがあります。まちづくりの宿命でもあるのですが、おそらくそうした事態がこの松岡城址でも起きたのかなーと思います(勝手な推察なので、違ったらすみません)。
特に人口規模の小さい市町村ですと、なおさら職員の個の力がダイレクトに行政運営に反映されます。全国的に見ても頑張っている市町村とそうではない市町村の差が生じているはこのためです。
わたしが在籍していた自治体も担当者のレベルによって推進力が異なるので、企画系であればなおさら、能力の差が地域の付加価値向上に直結しますね。能力の差をいかすのがチームなのですが、東日本大震災やコロナ対策など、別業務に追われてしまいチームとしても継続するのが難しいかったのかもですね。
綺麗にハード面は整備されているので、あとはソフト的にどうできるかだと思うんですよね。ハード面としては、一部で石畳をアスファルトにて補修しちゃってるものの、塀も門構えが整っているので街並みが美しく見えます。
お城跡は、ほぼ竹藪になってしまっているので、本丸まで登ってみよう!とは気が起きないですが、規模からして観光地になり得るのでは?と思うところ。
都市計画上は無指定(非線引き)

無指定とは、市街化を抑制する市街化調整区域とは異なり、特に都市計画・建築基準法上の制限は無い地域となります。高萩市の場合には、市街化区域と市街化調整区域とを分ける”区域区分”を指定していないため、松岡城があったエリアは特段の都市計画上の指定がないため、比較的建築の自由度は高いです。

ですので、農地法等の別法に基づく制限が無い限りは容積率200%、建蔽率60%の範囲内で観光地には必要な物販店や飲食店の建築が可能となります。
とはいえ課題としては、主要駅がある高萩駅からは約3.5kmほど離れているため、徒歩では厳しいと言わざるを得ないため、少なくともシェアサイクルやカーシェアが必要な状況にあると思われます。
観光地化の難しさ
なぜ、人が観光に来るのかといえば、歴史的な街並みや城跡(石垣や土塁、堀など)を見たいか、大切な人と一緒の時間を過ごしたいから、住んでいる地域以外の歴史や文化に触れてみたいから、そのようなところだと思います。
その上で、高萩市や茨城県北部地域の名産を売っている物販店、休憩できる飲食店があれば、それで観光地が成立するわけです。
わたしも行政経験の中でまちづくり活動の難しさを知っているので、あまり大層なことは言えませんが、リスクを取って真剣にやる人をつくるか、持ってくるしかない、その上でリスクを可能な限り低くしてあげるのが、地域住民・銀行・行政などの役割です。
とても教科書的で単純な仕組みに見えますが、この中に内在している”個々の質”については、どうしようも無い部分なので最も困難なリスクを抱えていますが、大抵は競争相手となる店舗等が増えていけば、勝手に質が上がっていくので、ほぼ解決できるようには思います。
最も重要なのは、最初にまとめる役割となる方とプレイヤー、それから行政・地域による支援です。また、地域にとっては、周辺地価が上がる可能性や地域経済が循環する仕組みとなるためメリットの方が高いように見えますが、現状維持を望む居住者のマインドを少しづつ変化させていく努力がとても大切でかつ苦労する業務となるので、全国的にまちづくりが成功している例としては、元から観光地であった場所が多いです。それでもコロナによる観光客減少の影響もあってか観光地の成功は相当難しいようです。
ですので、観光地として整備されていない地域を再整備して成功している例は少ないです。
何を持って成功とするのかの捉え方は人によって様々ですが、最終的にはGDP増加か、若しくは人口減少に伴う下げ幅をどの程度を抑えられるのか。かなと思います。
とはいえですが、仕組みは単純ですので、誰かがリスクを取っていけば、観光地化が可能です。この”誰かが”が一番重要なんですけどね。
わたしもプレイヤーとしてまちづくりとして携わったことがないためあまり言えた立場ではないですが、この水戸からいわき周辺が魅力の詰まった地域とならないか考えて行動していきたいと思います。
それではまた〜〜♪