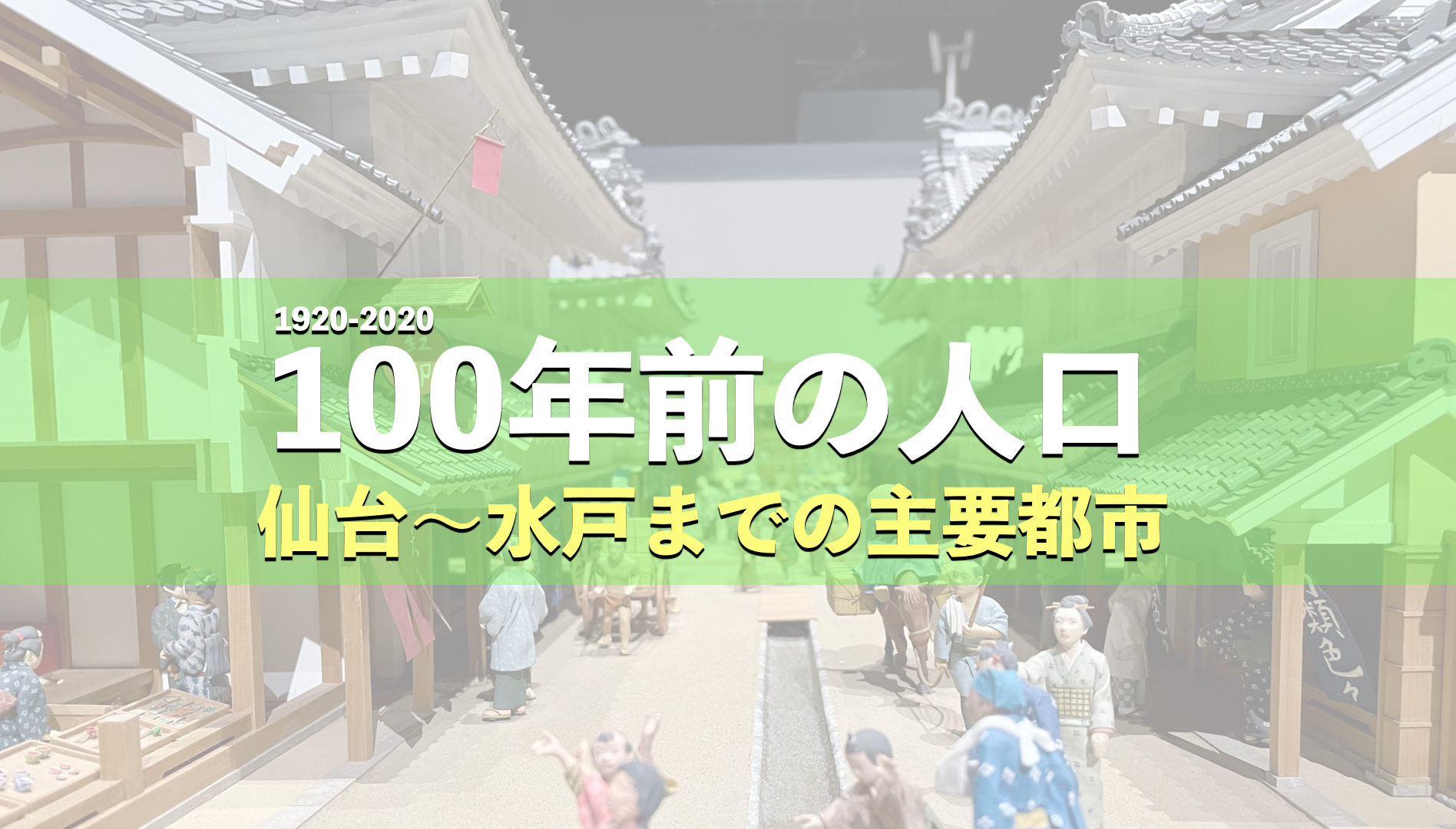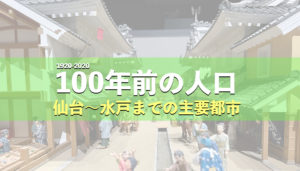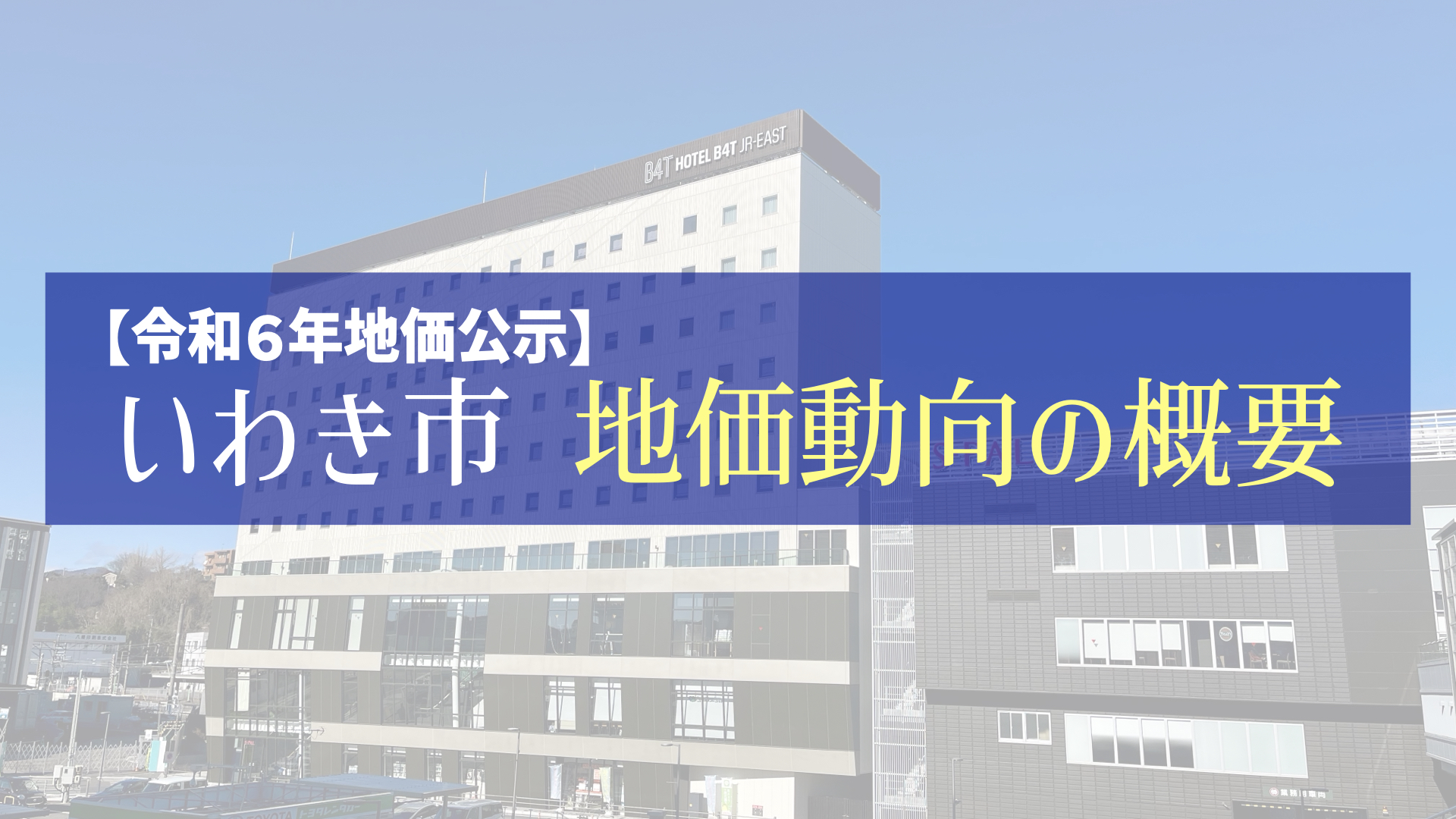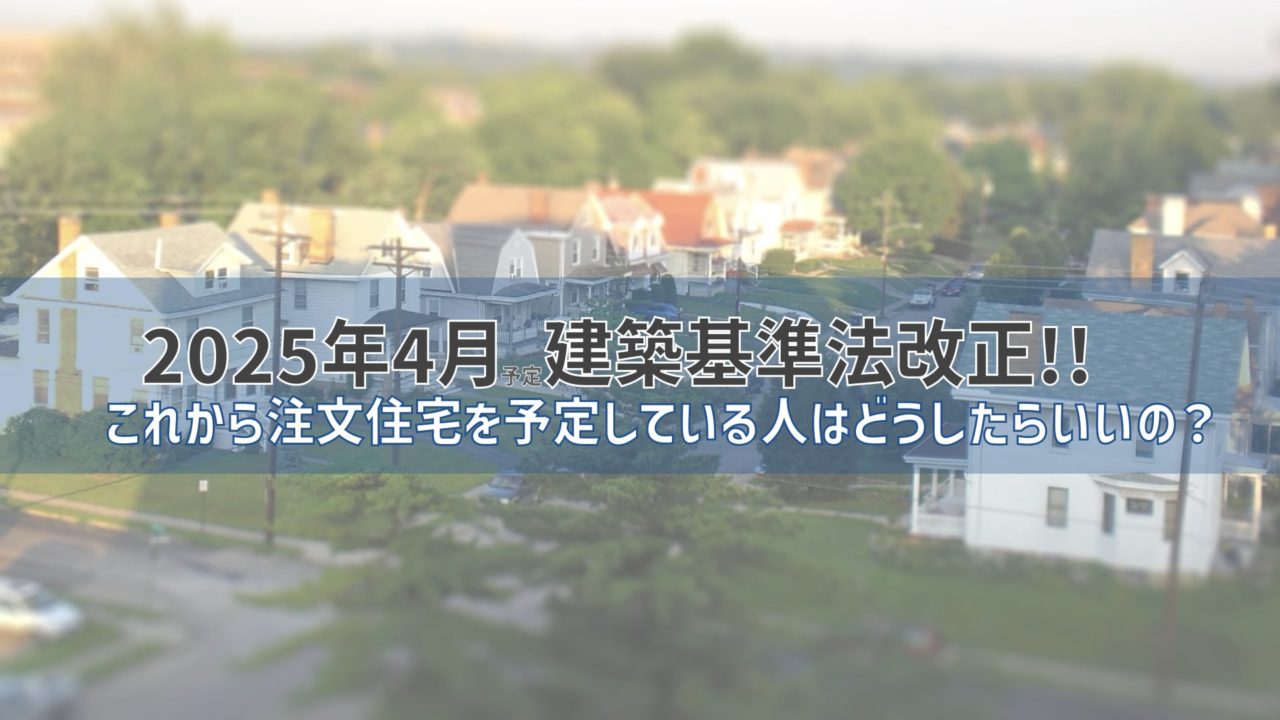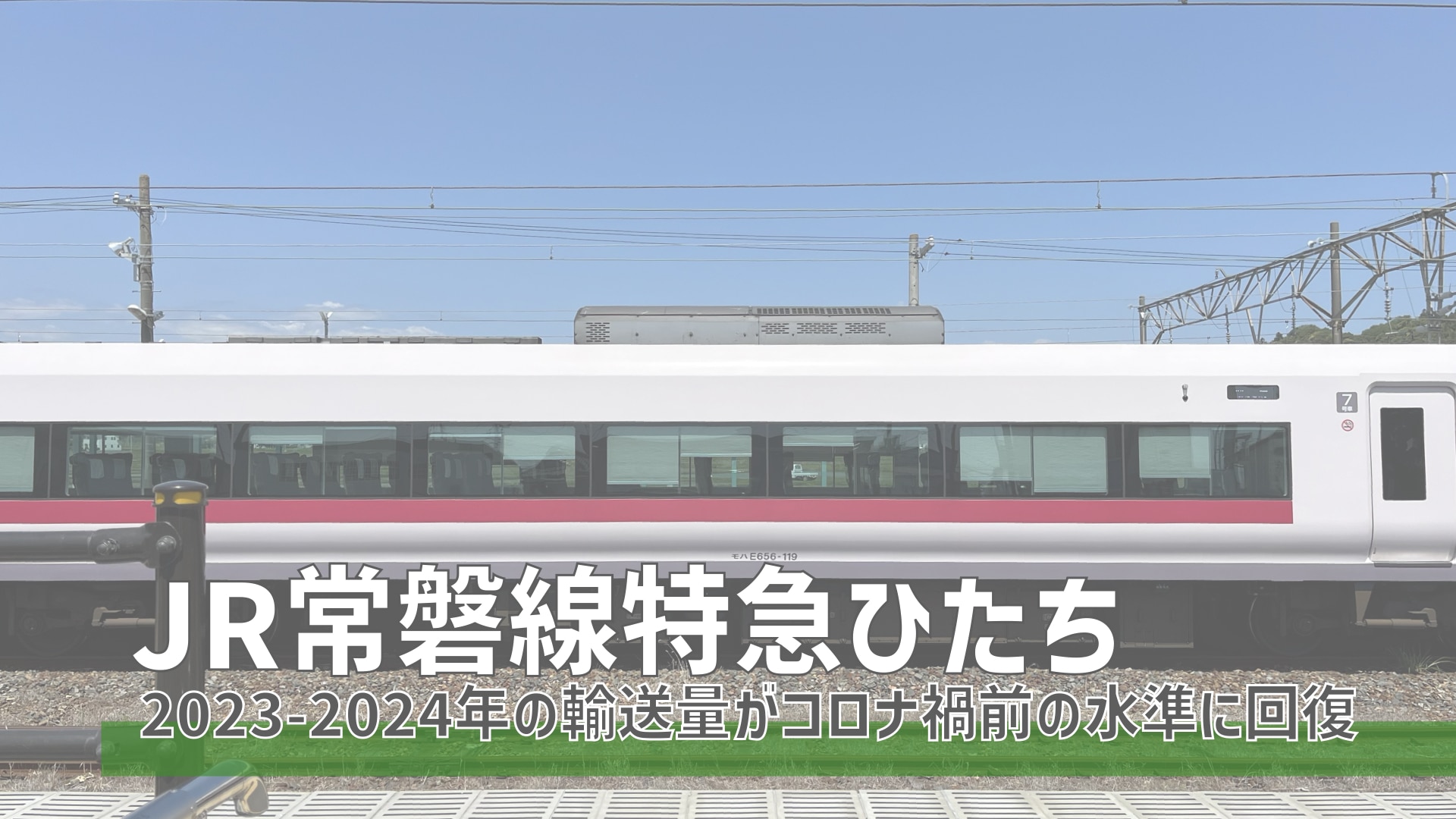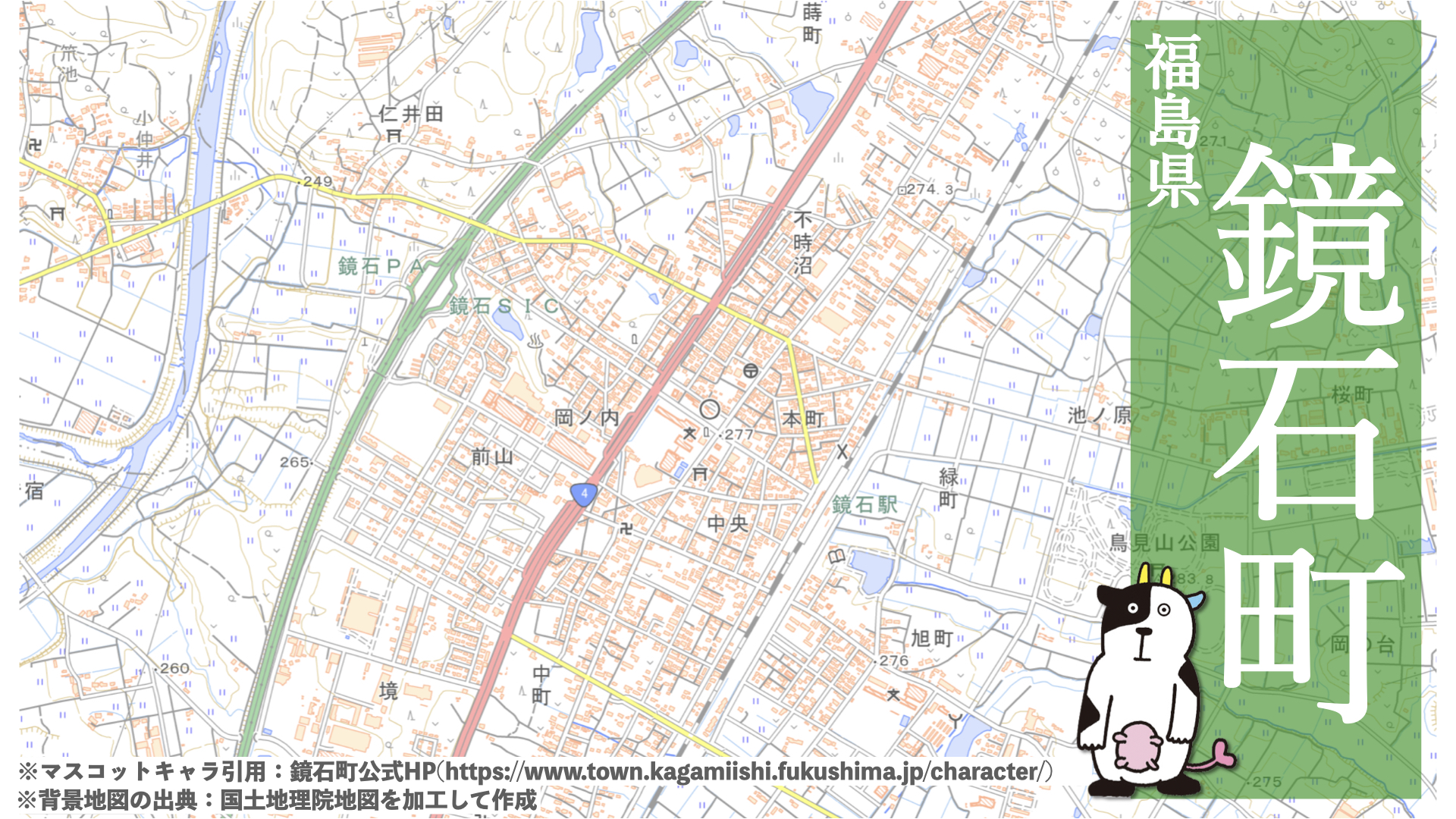この記事では、各都市の100年前(1920年)の人口を大正9年に行われた国勢調査をもとに掲載しています。100年前の人口を見ると、どこが拠点でどの町・村同士が合併したのかが一目で分かるので、まちづくりでの活用や各町・村の歴史を知る手がかりとなります。
いつも当サイト(UPS)をご覧いただきありがとうございます。
当サイトでは”まち”の稼ぐ力を伸ばすために、水戸から仙台エリアにかけての街の魅力や情報を発信しています。
現在はWEBを中心に活動していますが、近々、拠点を設けてまちづくりを行っていきたいと考えていますので、応援して頂ければ嬉しいです♪→サイトのブックマーク登録&インスタフォローをお願いします☆エンジェル投資家さんも随時募集しています♪
まとめ(1920-2020)
| 都市名 | 1920年 *中心都市 | 2020年 | 増加率 |
|---|---|---|---|
| 日本全体 | 55,963,053人 4.89人/世帯 *東京市2,173,201人 | 126,146,099人 2.21人/世帯 | 225.4% |
| 仙台市 | 175,587人 5.1人/世帯 *仙台市118,984人 | 1,096,704人 2.1人/世帯 | 624.6% |
| 相馬市 | 25,102人 5.3人/世帯 *中村町8,013人 | 34,865人 2.5人/世帯 | 138.9% |
| 南相馬市 | 51,906人 5.7人/世帯 *原町8,697人 | 59,005人 2.2人/世帯 | 113.7% |
| いわき市 | 210,587人 4.9人/世帯 *平町20,175人 | 332,931人 2.4人/世帯 | 158.1% |
| 北茨城市 | 38,559人 4.4人/世帯 *北中郷村10,265人 | 41,801人 2.5人/世帯 | 108.4% |
| 日立市 | 68,323人 4.2人/世帯 *日立村25,263人 | 174,508人 2.2人/世帯 | 255.4% |
| 東海村 | 6,804人 4.9人/世帯 | 37,891人 2.4人/世帯 | 556.9% |
| ひたちなか市 | 36,370人 4.7人/世帯 *湊町11,753人 | 156,581人 2.3人/世帯 | 430.5% |
| 水戸市 | 88,687人 4.9人/世帯 *水戸市39,363人 | 270,685人 2.2人/世帯 | 305.2% |
(注)1920年人口の区域は村の字の一部編入を考慮していないため現在の行政区域と一部異なる。
仙台市の人口増加率が624.6%ととても高い伸び率です。
1920年ごろの中心都市の仙台市(旧仙台市のエリア)の人口は118,984人、将来の合併を踏まえたエリアの人口は175,587人ですから大きく成長していることが分かります。
仙台市の場合には、東北地方の中心都市として交通の要所であったことや行政官庁の支庁や企業の支店経済による影響が大きいと考えられます。
一方で同じく県庁所在地の水戸市の場合には増加率は約3倍とあまり成長していないことが分かります。
これは、隣接するベットタウンのひたちなか市やその隣の東海村の人口が大きく伸びていることや、東京都・宇都宮市との距離に近さなどから、企業の支店経済の都市として発展し難かった点があるかと思います。とはいえ、同一都市圏のひたちなか市や東海村は人口が大きく伸びていますから、俯瞰的に捉えれば都市圏全体としては大きく成長したと考えられます。
*東海・ひたちなか・水戸の人口推移:1920:131,861人→2020:465,247人(352.8%増加)
日立市の場合には、行政運営上は非効率と思える合併(縦長の合併)をしながらも、約2.6倍ほど人口が増加しているので、日本全体の平均に比べると成長したといえると思います。
一方で相馬市や南相馬市は、地理的要因(中心都市:仙台や福島への距離の長さ)などから、思ったほど経済が伸びず高度経済成長期においても大都市に人口を供給し続けていたことが想定されます。
同様に北茨城市も地理的要因(水戸・日立との距離感、いわき市の未発展など)から、都市部への人口供給拠点となってしまっていた感があります。
もっとも課題があったのはいわき市です。
いわき市が合併する前の大正9年(1,920年)には、将来のいわき市のエリア内で約21万人の人口(今回、抽出した中で最大の人口)を有していましたが、2020年には約33万人と1.5倍程度しか人口が伸びていません。
いわき市の合併は1966年ですから、1920年から46年後に合併し、その後、現代までの約54年間(2020年まで)で、あまり人口が増加しなかったことになります。
いわき市も同様に高度経済成長期において、首都圏への人口供給拠点となっていたのは想定できます。
とはいえ、都市機能の発展の伴わない税投資が行われたことが考えられ、想定ですが面積規模が大き過ぎた合併のため、地域の不公平感なく分散型投資を行ったことが要因となり、中途半端な都市に成長してしまったのだと考えられます。
*歴史にIfはありませんが、周辺都市に比べ大きい税投資を上手に重点配分(1920年時点での中心都市:平・小名浜・湯本・四倉など)を行っていれば、1920年時点から約2〜3倍程度の人口増加率、人口にして40〜60万都市の成立は可能だったかもしれません。そうすれば、常磐線沿線の景色は違っていたでしょう。
ということで、今から約100年となる1920年と現代(2020年)を比較しました。
いずれの都市(仙台を除く)も、今後は出生率の低下や継続的な大都市圏への人口移動に伴い人口が急速に減少していきます。
特に地方部は2040年頃までの歪な人口構造(高齢化率の異常の高さ)を耐えなければならない時代に突入するため、必然的にこれまでの非効率な税投資から効率的な税投資(=都市をダイエット)にシフトしますから、今自分の年齢から20年後にどこで住みたいのか、どのような仕事をしているのか、どのようなライフスタイルなのかよくよく考えて都市を選択していくことが必要になると考えられます。
それでは以上となります。それではまた〜〜〜!!
宮城県
【仙台市】
1920-2020年の人口増減:+921,117人
| 合併 | 1920 | 2020 | 2022.6 | |
|---|---|---|---|---|
| 仙台市 | 175,587人,34,351世帯 | 1,096,704人,525,455世帯 | 1,098,309人,537,876世帯 | |
| 仙台市 | 118,984人,21,985世帯 | |||
| 西多賀村 | 1932 | 3,325人,533世帯 | ||
| 中田村 | 1941 | 4,167人,654世帯 | ||
| 六郷村 | 1941 | 4,884人,746世帯 | ||
| 七郷村 | 1941 | 7,033人,1,165世帯 | ||
| 岩切村 | 1941 | 4,089人,680世帯 | ||
| 高砂村 | 1941 | 7,404人,1,173世帯 | ||
| 生出村 | 1957 | 3,555人,531世帯 | ||
| 宮城町 | 1987 | 7,736人,1,068世帯 | ||
| 広瀬村 | 1955 | 3,829人,556世帯 | ||
| 大沢村 | 1955 | 3,907人,512世帯 | ||
| 泉市 | 1988 | 10,134人,1,540世帯 | ||
| 七北田村 | 1955 | 5,147人,828世帯 | ||
| 根白根村 | 1955 | 4,987人,712世帯 | ||
| 秋保町 | 1988 | 4,276人,606世帯 |
(注)1920年人口は村の字の一部編入を考慮していないため現在の行政区域と一部異なる。
福島県
【相馬市】
1920-2020年の人口増減:+9,763人
| 合併 | 1920 | 2020 | 2022.5 | |
|---|---|---|---|---|
| 相馬市 | 25,102人,4,762世帯 | 34,865人,13,875世帯 | 33,558人,14,360世帯 | |
| 中村町 | 1954 | 8,013人,1,657世帯 | ||
| 大野村 | 1954 | 3,600人,555世帯 | ||
| 飯豊村 | 1954 | 3,212人,518世帯 | ||
| 八幡村 | 1954 | 2,594人,448世帯 | ||
| 山上村 | 1954 | 1,716人,292世帯 | ||
| 玉野村 | 1954 | 379人,673世帯 | ||
| 日立木村 | 1954 | 1,991人,333世帯 | ||
| 磯部村 | 1954 | 1,881人,286世帯 |
(注)1920年人口は村の字の一部編入を考慮していないため現在の行政区域と一部異なる。
【南相馬市】
1920-2020年の人口増減:+7,099人
*東日本大震災による原発事故の影響前(2010年)の人口は、約7.1万人
| 合併 | 1920 | 2020 | 2022.5 | |
|---|---|---|---|---|
| 南相馬市 | 51,906人,9,071世帯 | 59,005人,26,349世帯 | 57,654人,26,427世帯 | |
| 原町市 | 2006 | 25,040人,4,430世帯 | 45,046人,21,037世帯 | |
| 原町 | 1954 | 8,697人,1,737世帯 | ||
| 太田村 | 1954 | 3,122人,510世帯 | ||
| 大甕村 | 1954 | 3,867人,603世帯 | ||
| 高平村 | 1954 | 2,913人,453世帯 | ||
| 石神村 | 1956 | 6,441人,1,127世帯 | ||
| 小高町 | 2006 | 14,013人,2,401世帯 | 3,629人,1,619世帯 | |
| 小高町 | 1954 | 6,197人,1,131世帯 | ||
| 福浦村 | 1954 | 3,653人,580世帯 | ||
| 金房村 | 1954 | 4,160人,690世帯 | ||
| 鹿島町 | 2006 | 12,853人,2,240世帯 | 10,330人,3,693世帯 | |
| 鹿島町 | 1954 | 2,908人,575世帯 | ||
| 真野村 | 1954 | 2,793人,491世帯 | ||
| 八沢村 | 1954 | 2,584人,401世帯 | ||
| 上真野村 | 1954 | 4,568人,773世帯 |
(注)1920年人口は村の字の一部編入を考慮していないため現在の行政区域と一部異なる。
【いわき市】
1920-2020年の人口増減:+122,351人
| 合併 | 1920 | 2020 | 2022.6 | |
|---|---|---|---|---|
| いわき市 | 210,580人,43,244世帯 | 332,931人,141,411世帯 | 326,943人,141,473世帯 | |
| 平市 | 1966 | 50,099人,9,886世帯 | 92,768人,42,025世帯 | |
| 平町 | 1937 | 20,175人,4087世帯 | ||
| 飯野村 | 1950 | 2,830人,518世帯 | ||
| 夏井村 | 1954 | 2,481人,463世帯 | ||
| 高久村 | 1954 | 2,234人,365世帯 | ||
| 豊間村 | 1954 | 2,922人,585世帯 | ||
| 赤井村(小川町) | 1955 | 9,359人,2,031世帯 | ||
| 平窪村 | 1937 | 2,950人,483世帯 | ||
| 神谷村 | 1950 | 3,267人,622世帯 | ||
| 草野村 | 1954 | 3,881人,732世帯 | ||
| 磐城市 | 1966 | 21,085人,3,997世帯 | 81,834人,34,468世帯 | |
| 小名浜町 | 1954 | 6,632人,1,448世帯 | ||
| 泉村 | 1954 | 3,782人,660世帯 | ||
| 渡辺村 | 1954 | 1,949人,377世帯 | ||
| 江名村 | 1954 | 4,667人,811世帯 | ||
| 鹿島村 | 1953 | 1,801人,321世帯 | ||
| 玉川村 | 1941 | 2,254人,380世帯 | ||
| 勿来市 | 1966 | 25,787人,5,447世帯 | 47,510人,19,920世帯 | |
| 鮫川村 | 1955 | 4,903人,964世帯 | ||
| 錦村 | 1955 | 3,205人,628世帯 | ||
| 山田村 | 1955 | 3,972人,840世帯 | ||
| 窪田村 | 1955 | 8,101人,1,809世帯 | ||
| 川部村 | 1955 | 5,606人,1,206世帯 | ||
| 常磐市 | 1966 | 23,003人,5,082世帯 | 32,734人,14,019世帯 | |
| 湯本村 | 1954 | 11,979人,2,713世帯 | ||
| 磐崎村 | 1954 | 11,024人,2,369世帯 | ||
| 内郷市 | 1966 | 21,799人,4,723世帯 | 24,656人,11,231世帯 | |
| 内郷村 | 1966 | 20,174人,4,434世帯 | ||
| 箕輪村(好間町) | 1955 | 1,625人,289世帯 | ||
| 四倉町 | 1966 | 14,135人,2,801世帯 | 14,372人,5,926世帯 | |
| 四ツ倉町 | 1955 | 6,078人,1,292世帯 | ||
| 大浦村 | 1955 | 3,672人,672世帯 | ||
| 大野村 | 1955 | 4,385人,837世帯 | ||
| 好間村 | 1966 | 18,624人,4,058世帯 | 12,439人,5,675世帯 | |
| 小川町 | 1966 | 3,973人,795世帯 | 6,464人,2,411世帯 | |
| 上小川村 | 1955 | 2,111人,424世帯 | ||
| 下小川村 | 1955 | 1,862人,371世帯 | ||
| 遠野町 | 1966 | 8,991人,1,787世帯 | 4,871人,1,791世帯 | |
| 上遠野村 | 1955 | 5,104人,1,055世帯 | ||
| 入遠野村 | 1955 | 3,887人,732世帯 | ||
| 川前村 | 1966 | 4,914人,1,121世帯 | ||
| 田人村 | 1966 | 5,027人,1,045世帯 | 1,302人,557世帯 | |
| 田人村 | 1941 | 3,111人,650世帯 | ||
| 貝泊村 | 1941 | 751人,146世帯 | ||
| 石住村 | 1941 | 633人,131世帯 | ||
| 荷路夫村 | 1941 | 532人,118世帯 | ||
| 三和村 | 1966 | 6,788人,1,274世帯 | 2,518人,956世帯 | |
| 沢渡村 | 1955 | 1,584人,293世帯 | ||
| 三阪村 | 1955 | 2,606人,459世帯 | ||
| 永戸村 | 1955 | 2,598人,522世帯 | ||
| 久之浜・大久 | 1966 | 6,325人,1,208世帯 | 4,595人,2,094世帯 | |
| 久之浜町 | 1966 | 4,085人,841世帯 | ||
| 大久村 | 1966 | 2,240人,367世帯 |
(注)1920年人口は村の字の一部編入を考慮していないため現在の行政区域と一部異なる。
茨城県
【北茨城市】
1920-2020年の人口増減:+3,242人
| 合併 | 1920 | 2020 | 2022.6 | |
|---|---|---|---|---|
| 北茨城市 | 38,559人,8,835世帯 | 41,801人,17,042世帯 | 40,629人,16,972世帯 | |
| 磯原町 | 1956 | 17,043人,4,102世帯 | ||
| 北中郷村 | 1955 | 10,265人,2,427世帯 | ||
| 華川村 | 1955 | 6,778人,1,675世帯 | ||
| 大津町 | 1956 | 4,556人,995世帯 | ||
| 関南村 | 1956 | 2,056人,422世帯 | ||
| 関本村 | 1956 | 3,710人,790世帯 | ||
| 平潟町 | 1956 | 2,218人,501世帯 | ||
| 南中郷村 | 1956 | 8,976人,2,115世帯 |
【日立市】
1920-2020年の人口増減:+106,185人
| 合併 | 1920 | 2020 | 2022.6 | |
|---|---|---|---|---|
| 日立市 | 68,323人,16,297世帯 | 174,508人,77,911世帯 | 169,816人,77,359世帯 | |
| 日立村 | 25,263人,6,108世帯 | |||
| 高鈴村(助川町) | 1939 | 8,401人,2,090世帯 | ||
| 多賀町 | 1955 | 11,342人,3,010世帯 | ||
| 坂上村 | 1941 | 2,772人,582世帯 | ||
| 国分村 | 1938 | 3,499人,712世帯 | ||
| 鮎川村 | 1938 | 2,249人,483世帯 | ||
| 河原子村 | 1938 | 2,822人,651世帯 | ||
| 日高村 | 1955 | 2,293人,509世帯 | ||
| 久慈町 | 1955 | 5,686人,1,220世帯 | ||
| 中里村 | 1955 | 3,130人,693世帯 | ||
| 坂本村 | 1955 | 1,975人,429世帯 | ||
| 東小沢村 | 1955 | 1,601人,323世帯 | ||
| 中里村 | 1955 | 3,103人,693世帯 | ||
| 十王町 | 2004 | 5,529人,1,222世帯 | ||
| 櫛形村 | 1955 | 3,355人,754世帯 | ||
| 黒前村 | 1955 | 2,174人,468世帯 |
(注)1920年人口は村の字の一部編入を考慮していないため現在の行政区域と一部異なる。
【東海村】
1920-2020年の人口増減:+31,087人
| 合併 | 1920 | 2020 | 2022.6 | |
|---|---|---|---|---|
| 東海村 | 6,804人,1,383世帯 | 37,891人,15,849世帯 | 37,849人,15,819世帯 | |
| 村松村 | 1955 | 3,878人,748世帯 | ||
| 石神村 | 1955 | 2,926人,635世帯 |
(注)1920年人口は村の字の一部編入を考慮していないため現在の行政区域と一部異なる。
【ひたちなか市】
1920-2020年の人口増減:+120,211人
| 合併 | 1920 | 2020 | 2022.6 | |
|---|---|---|---|---|
| ひたちなか市 | 36,370人,7,769世帯 | 156,581人,66,754世帯 | 155,516人,67,703世帯 | |
| 勝田市 | 1994 | 17,581人,3,555世帯 | 130,889人,56,354世帯 | 130,075人,57,257世帯 |
| 勝田村 | 1940 | 3,073人,658世帯 | ||
| 中野村 | 1940 | 3,362人,712世帯 | ||
| 川田村 | 1940 | 2,319人,450世帯 | ||
| 前渡村 | 1954 | 4,847人,892世帯 | ||
| 佐野村 | 1954 | 3,980人,843世帯 | ||
| 那珂湊市 | 1994 | 18,789人,4,214世帯 | 25,692人,10,409世帯 | 25,041人,10,446世帯 |
| 湊町 | 1954 | 11,753人,2,720世帯 | ||
| 平磯町 | 1954 | 7,036人,1,494世帯 |
(注)1920年人口は村の字の一部編入を考慮していないため現在の行政区域と一部異なる。
【水戸市】
1920-2020年の人口増減:+181,998人
| 合併 | 1920 | 2020 | 2022.6 | |
|---|---|---|---|---|
| 水戸市 | 88,687人,18,265世帯 | 270,685人,122,598世帯 | 269,776人,124,968世帯 | |
| 水戸市 | 39,363人,8,189世帯 | |||
| 常磐村 | 1933 | 5,542人,1,201世帯 | ||
| 緑岡村 | 1952 | 3,954人,812世帯 | ||
| 上大野村 | 1952 | 2,300人,477世帯 | ||
| 渡里村 | 1955 | 2,911人,503世帯 | ||
| 吉田村 | 1955 | 2,264人,487世帯 | ||
| 柳河村 | 1955 | 2,037人,410世帯 | ||
| 国田村 | 1957 | 2,637人,564世帯 | ||
| 飯富村 | 1957 | 2,612人,512世帯 | ||
| 酒門村 | 1955 | 2,692人,510世帯 | ||
| 赤塚村 | 1958 | 6,823人,1,408世帯 | ||
| 山根村 | 1955 | 2,285人,497世帯 | ||
| 上中妻村 | 1955 | 2,044人,405世帯 | ||
| 河和田村 | 1955 | 2,494人,506世帯 | ||
| 常澄村 | 1922 | 7,767人,1,591世帯 | ||
| 下大野村 | 1955 | 2,857人,571世帯 | ||
| 大馬村 | 1955 | 2,076人,432世帯 | ||
| 稲荷村 | 1955 | 2,834人,588世帯 | ||
| 内原町 | 2005 | 7,785人,1,601世帯 | ||
| 下中妻村 | 1955 | 2,399人,527世帯 | ||
| 中妻村 | 1955 | 2,054人,412世帯 | ||
| 鯉淵村 | 1955 | 3,332人,662世帯 |
(注)1920年人口は村の字の一部編入を考慮していないため現在の行政区域と一部異なる。